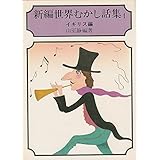『自殺クラブ』 (福武文庫) ロバート・ルイス スティーヴンソン 河田 智雄

「新アラビア夜話」から「自殺クラブ」と「ラージャのダイヤモンド」の2編。どちらもボヘミアのフロリゼル王子が関わっていて、でも目立っているのは「自殺クラブ」のほう。各編はさらに小さく分かれていて、場面が飛んだりするとたまに「あれ?」って思ったことも。
「自殺クラブ」は死にたいけど自分で命を絶つのは怖いという会員で成り立っているクラブ。お忍び中の王子がそのメンバーと偶然出会ってクラブに潜入して、その実態を目の当たりにして、クラブの消滅に命をかける話。ドキドキハラハラです。
「ラージャのダイヤモンド」はとても高価なダイヤモンドを手にしたことによって、次から次へと、たくさんの人の人生が狂っていく話。喜劇のような雰囲気。
お勧めですよぅ。
『ケルトの神話—女神と英雄と妖精と』 (ちくま文庫) 井村 君江

ややこしくて大変でした。面白かったけど、理解して覚えるなんてとんでもないことです。読んでると「本当にあった話」に思えて混乱しました。ドゥルイド僧と誓約のはなしが面白かったです。あれこれ言わなくてもこの手のものが好きならタイトルと筆者で良さがわかるでしょう、ということで(逃)
『ガラスびんの中のお話』 ベアトリ・ベック 川口 恵子

描写がすごく素敵でした。丁寧に泉の水に糸を通した首飾り、とか。そんなところは読んでてとても楽しいです。でも話は、救われなかったり、だからなんなの、と思うような終わり方だったり、あんまり好みじゃないかもしれない。でもやっぱり描写がすごいし、妖精の役割とかは面白かったです。
そんなふうに思いながら、あとがきを読んで、納得しました。けっこうこれ、根が深いんですね。原作者の生育環境とか、意図してなのかそうでないのかはわかりませんが、ずいぶん色濃く反映されてるらしい。それを踏まえて、もう一度読んだら面白いかもしれませんね。
『新編世界むかし話集 1イギリス編』

とっても面白かった! 語り口も女性的で優しく丁寧なのでスルッと入ってきました。
ジャックと豆の木のお話が入っていて、絵本とかじゃなくてちゃんと読んだのは初めてかな。なんというかこれに限らず、うすのろの他種族からは盗みを働いて良い……みたいな話が多いですね! こんな人がいてこんな事をしてそして死にました。という構成が多いように感じて、めでたくもないしだからどうした……という読後感に慣れるまでちょっと時間がかかりました。
でも、どれも実話のように語られていて、現在もここには石碑がありますとか書かれているととてもテンションが上りました。それぞれの地理とか詳しく知りたくなります。英語わかんないから難しいだろうけど…。他の国々の編も出てるので、見かけたら読もうと思います。
『語り聞かせのためのむかしばなし集』 村上 春夫

いくつかの昔話と、語り聞かせのためのポイントと、遊びに発展させるポイントがわかりやすく書かれていました。複数の子どもを相手に話し聞かせることが前提になっているので、そういう職業の人や興味のある人にはとてもいい本だと思います。読み物としてはやっぱりちょっと物足りなかった。でもお話を全部覚えないと語り聞かせられないわけで、そのあたり「すごいなぁ」と思います。
『死刑囚の記録』 (中公新書 (565)) 加賀 乙彦

面白かったです。興味深かったといったほうがいいかもしれませんが。すらすらと読めてひさしぶりに数日で読み終えるということをしました。ほとんどを○○事件の誰は何をやって拘置所ではこんなようすで筆者との関係はどうだった、というのがタイトルどおりに記録されている感じです。文章が生きている、ように感じました。小説も書いているそうなのでそちらも気になりますが、本文中でそれを言うときは妙に宣伝ぽくて素直に読みたいと思わなかったです。ひねくれてんのかな。
いろいろ思うところがあります。筆者の意見に賛成だったり反対だったり、死刑囚の言葉に思うところがあったり。でも最後の「死刑は残酷だからやめよう」っていうのは、だったら先に殺人は残酷だからやめようっていいたい。研究のためか治療する側としてか殺人犯に対してとても、こう、心を開いている方ですね。そのあたり読んでてたまに不快に思ったりしました。私は自分や大切な人を殺されたくないので殺人する人は受け入れません。といっても本文中に犯罪を煽るようなところがあるとかではなくて、善悪に関してほとんど触れていない感じで。本の内容にとても合っていると思います。そんなところがあってもとても面白い本でした。なにをどう思うかはそれぞれとしても、ぜひ読んでおきたい1冊です。
『影をなくした男』 (岩波文庫) Adelbert von Chamisso 池内 紀

望むものは何でも出てくるポケットと自分の影を交換した男。なんでも出せる男に人々は群がり寄ってくるけれど、影がないことに気がつくと…。ものすごーく面白いです!
『不思議の国のアリス』 (ちくま文庫) ルイス キャロル

アリスといえば柳瀬さん。買い直した思い出があります。言葉遊びの部分が素晴らしい。訳されたものを読んでも意味がわかる感じで面白かったです。意訳…なのかなぁ? 他の人の訳では意味がわからなくて読むのが苦痛だったけど。どっちがいいかはわらないけど柳瀬さんがお勧めです。
『チャンセラー号の筏』 (集英社文庫—ジュール・ヴェルヌ・コレクション) Jules Verne 榊原 晃三

人生で初のヴェルヌ。小説読んで吐き気をもよおした初めての作品。筏で漂流するサバイバル物。
『フランス笑話集』 (1981年) (現代教養文庫〈1049〉) 奥平 堯

読み応えはあるとは言えないけど、軽快に読めました。ぺてん師、いたずら者、おろか者、酒飲みと食いしん坊、知恵者と機転に分類されています。なんていうか、笑うに笑えない話(いい人が死んじゃったり)が多かったような。外国のお話のせいだろうか。ずるいほどに楽に生きていけるような話しとか、いいのかこれ…。でも、生活の様子とかがリアルに自然に書かれていて面白かったです。
『カルパチアの城』 (集英社文庫—ジュール・ヴェルヌ・コレクション) Jules Verne 安東 次男

陰鬱とした雰囲気がすごかった。描写が細かくて臨場感があるのはさすが、いつもどおり。でも最初の地形とかの説明は眠くなっちゃった。有名な冒険小説の類とはちょっと違って、それは解説に詳しくあるのでおいといて。女性をめぐって、っていうのが珍しいなーと思いました。
大きく分けて前後編。前半は打ち捨てられたカルパチアの城のいわく、裾野に広がる森、小さな村、迷信、村人などが書かれています。ある日、望遠鏡を手に入れた羊飼いが、誰もいないはずの古城から煙が上がっているのを発見。そこから幽霊騒ぎがはじまり、勇気あるものが確かめに行って恐ろしい目にあう。後半は真打登場とばかりに主人公格の紳士が登場。城の主と、ある女性との三角関係を独白。城に乗り込み、苦難をこえて城の主と相対する。
ひとつひとつが地に足が着いていて、やっぱりヴェルヌだなーと思います。村人が「幽霊だ化け物だ」って騒いだものも、しっかりと種明かしがあるし。前半のほうが好きかな? はじめはダルいと思った描写も、今では映像となって浮かぶほど印象に残っています。
『カフカ傑作短篇集』 (福武文庫—海外文学シリーズ) 長谷川 四郎

ちょっと難しいところもあったけど、面白かった! 「万里の長城」と「火夫」が特に好きだったな。「猟師グラッホス」「橋」「ポザイドン」も。そして「飢餓術師」。巻末の解説が、カフカの解説というよりは、訳者の解説だったのには「ぅえ?」と思いましたが、褒めちぎってるだけあって上手いんだろうな〜と思いました。難解な話とかでも文章にぐいぐいと引っ張られる感じ。「火夫」とかすごく楽しくて面白かったです。カフカ入門に相応しいらしいこの本、確かにもっとカフカを読んでみたくなりました。